原則と例外(S22.9.13発其17)
「1項(毎週1日)が原則であり、2項(4週間に4日以上)は例外であることを強調し徹底させること」
1歴日の休日 通達(S23.4.5基発535(35条関係))
「休日とは単に連続24時間の休業であるは、あるいは暦日を指し、午前零時から午後12時までの休業と解すべきか」という問いに対する回答は、「後段の通り」
すなわち、「休日とは暦日を指し、午前零時から午後12時までである」
1昼夜交替勤務の場合 通達(S23.11.09基収2968(35条関係))(ただし、解かりやすくするため、内容を若干変更した))
「午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す1昼夜交代勤務の場合において、労働日、非番日、労働日、非番日、労働日、非番日と続く場合、労働基準法上の休日はどのように与えるべきか」という問に対して、回答は、「6日目の非番日が24時間継続していてもこれは休日ではなく、その日の深夜0時から翌日午後12時までを別途に休日として与えなければならない。(実際には、休日が終わる午後12時から午前8時までの8時間も不就労とし、そこから、労働日、非番日・・・と続けることになる)
交替制の場合の休日 通達(S63.3.14基発150号(35条関係))
「休日は暦日によるべきことが原則であるが、
例えば、8時間3交替連続作業のような場合において暦日休日制の解釈をとることは、連続24時間以上の休息が2暦日にまたがる際は、1週2暦日の休日を与えなければならないこととなり、1週1日の週休制をとった立法の趣旨に合致しないこととなる。
そこで、番方編成による交替制における「休日」については、次のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取扱う」
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。 |
休日の特定 (S63.3.14基発150)
「35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから、就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけでなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。
常時10人未満の労働者を使用する(就業規則の作成義務のない)事業においても、具体的に休日を定めるよう指導されたい」
休日の配慮 通達(S23.9.20基発1384号)、
「法35条2項の休日はいかなる4週間に区切っても、どの4週間にも必ず4回の休日が与えられていなければならないか」という問に対して、回答は
「法35条2項の規定は、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではない。
なお、特定の4週間を明確にさせるため、施行規則12条の2の2項により、その起算日を就業規則等で明らかにすることとされているので、留意すること」 |
休日の振替
休日の振替と代休 通達(S63.3.14基発150(35条関係2))
「就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができるか」という問いに対して、回答は、
「就業規則において休日を定めるとともに、別に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
以上によることなく、休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらない(すなわち、当初予定された休日における労働は割増賃金が発生する休日労働となる)」
休日の振替と時間外労働 通達(S63.3.14基発150(35条関係3))
「就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働になり、時間外労働に関する36協定および割増賃金の支払いが必要であることに注意されたい」
休日振替の手続 通達(S63.3.14基発150(35条関係4))
「業務等の都合により、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。
なお、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましいこと」 |
国民の祝日 (S41.7.14基発739)
「国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけをするのではなく、労働基準法は、毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務づけているが、この要件を満たす限り、国民の祝日に休ませなくても労働基準法違反とはならない。しかしながら、国民の祝日の趣旨および労働時間短縮の見地から、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもない」 |
休日の出張 通達(S33.2.13基発90(35条関係))
「日曜日の出張は、休日労働に該当するか」という問に対して、回答は、
「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは、休日労働として取扱わなくても差し支えない」
 月曜日朝にある本社の会議に出席するため、日曜日の夜行列車に乗って移動しても労働時間ではない。(ましてや休日労働でも深夜労働でもない。何曜日でも同じ) 月曜日朝にある本社の会議に出席するため、日曜日の夜行列車に乗って移動しても労働時間ではない。(ましてや休日労働でも深夜労働でもない。何曜日でも同じ)
ただし、出張命令による場合は、休憩時間と同じような扱いで拘束時間にはなる。よって、列車内で事故にあえば業務上災害
になりうる。
企業によっては、出張日当などの名目によって代価を支払うこともある。(ただしこれは、労働の対償ではないから賃金ではない)気のきいた上司であると、「列車内でレポートを書け、重要書類であるから常に見張っておけ」と特段の業務指示を出し、労働時間と認めてくれる場合がなきにしもあらずである。 |
全労働日の8割以上出勤
出勤率の悪い者は年次有給休暇の請求ができないということ。
| 全労働日 |
労働契約上、労働義務が課せられている日 |
=総暦日数 -
①就業規則その他によって定められた休日(労働してもしなくても関係なし) -
②使用者の責めに帰すべき事由による休業の日 -
③正当なストライキその他の争議行為より労務の提供がなされなかった日 |
|
出勤した日 |
実際に出勤した日及び出勤したと見なされる日(本来は欠勤ではあるが、労働者の故意や怠慢などによるものではなく、正規の手続きに基づいて取得した休業期間) |
=就業規則その他によって定められた労働日で実際に出勤した日 +
①年次有給休暇を取得した日 +
②業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 +
③育児・介護休業法による育児休業又は介護休業をした期間 +
④産前産後の休業した期間 |
「生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求して就業しなかった期間は、労働基準法上出勤したものとは見なされないが、当事者の合意によって出勤したものとみなすことも、もとより差し支えない」(S23.7.31基収2675)
「全労働日が零となる場合は、前年に労働日のあることを前提とする39条の解釈上、8割以上出勤するという法定要件を充たさないから、年次有給休暇の請求権は発生しない」(S27.12.2基収5783) |
最高裁判例{白石営林署事件、S48.03.02)}
「労基法39条1、2項の要件が充足されたときは、当該労働者は法律上当然に右各項所定日数の年次有給休暇の権利を取得し、使用者はこれを与える義務を負うのであるが、この年次休暇権を具体的に行使するにあたつては、同
法は、まず労働者において休暇の時季を「請求」すべく、これに対し使用者は、同条3項但書の事由が存する場合には、これを他の時季に変更させることができるものとしている。
かくのごとく、労基法は同条3項において「請求」という語を用いているけれども、
・年次有給休暇の権利は、同条1、2項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利であつて、労働者の請求をまつて始めて生ずるものではなく、また、
・(具体的な行使にあたって)同条3項にいう「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であつて、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。
年次有給休暇に関する労基法39条1項ないし3項の規定については、以上のように解されるのであつて、これに同条1項が年次休暇の分割を認めていることおよび同条3項が休暇の時季の決定を第一次的に労働者の意思にかからしめていることを勘案すると、労働者がその有する休暇日数の範囲で、具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条3項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によつて年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。
すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」
の観念を容れる余地はないものといわなければならない」]。 |
年次有給休暇と争議行為 (S27.7.25基収3821)
「昭和48年3月2日、労働基準法39条の解釈について最高裁第2小法廷判決(注:白石営林署事件)がなされたので、今後における同条の解釈適用は下記によって行う。
① 年次有給休暇の権利は、法定要件を充たした場合、法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない。同条4項の「請求」とは休暇の時季を指定するという趣旨であって、労働者が時季の指定をしたときは、客観的に同項ただし書き所定の事由(事業の正常な運営を妨げる場合)が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしない限り、その指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労の義務が消滅するものと解するのが相当である。このように解するならば、年次有給休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」というような観念を入れる余地はない。
⇒ 使用者は、時季を指定してきた年次有給休暇に対しては、これを承認するとかしないとかではなく、時季変更権を行使するか(行使できるのか)否かの選択しかない。
② 年次有給休暇を労働者がどのように利用するかは労働者の自由である。しかし、労働者がその所属の事業場においてその業務の正常な運営の阻害を目的として一斉に休暇を提出して職場を放棄する場合は、年次有給休暇に名を借りた同盟罷業(ストライキ)にほかならないから、それは年次有給休暇権の行使ではない。ただし、このようにいえるのは、当該労働者の所属する事業場で休暇闘争が行われた場合のことであって、他の事業場における争議行為に休暇をとって参加するような場合は、それを年次有給休暇の行使でないとはいえない」(S48.3.6基発110) 「39条の年次有給休暇は、労働者の勤続年数に応じて与えられる休息であり、就業しないでも賃金を受けることができるのであって、それは正常な労働関係にあることが前提とされているものである。
従って、労働者が年次有給休暇を争議行為に利用する目的で請求した場合には、法の趣旨とも相容れないものであるから、使用者は労働者の請求を拒否できるものと解される。すでに年次有給休暇を与えることを使用者が承認した後においても、労働者がその日に行われた争議に参加した場合には、使用者はその日を年次有給休暇として取り扱わなくても違法ではない。また、争議行為がなされた後、争議に参加した労働者よりその日を年次有給休暇に振替えることを請求された場合には、使用者はその日の争議行為が事業の正常な運営を妨げたと否とを問わず、振替えを拒否することができるのはいうまでもないが、使用者が労働者の要求を認めてその日を年次有給休暇に振替え、争議行為の行われた日に労働基準法所定の年次有給休暇を与えたこととして取り扱うことも差し支えない」
 文脈からいって、当該労働者が所属する事業場における争議行為のことであると解されるので、上記の判例とは矛盾しない。 文脈からいって、当該労働者が所属する事業場における争議行為のことであると解されるので、上記の判例とは矛盾しない。 |
請求できる日
「年次有給休暇は労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有
給休暇を請求する余地はないこと。
また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協定に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日にかかる賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じる」(H3.12.20基発712)
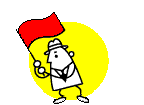 育児休業・介護休業期間中および65条による産前産後の休業期間中は、出勤したものとみなされるが、労働義務日ではないので、年次有給休暇そのものを申し出ることはできない。 育児休業・介護休業期間中および65条による産前産後の休業期間中は、出勤したものとみなされるが、労働義務日ではないので、年次有給休暇そのものを申し出ることはできない。
業務上の負傷・疾病により療養のために休業した期間中も出勤したものとみなされるが、これについては、年次有給休暇の取得はできるとされている。(ただし休業補償がなされるので、あえて有給休暇を取得する必要はないであろう)
長期休業中の場合の年次有給休暇(S24.12.28基発1456)
「その1 (業務上あるいは業務外の)負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を申し出たときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されことから、このような労働者に対して、申し出があれば年次有給休暇を与えなくてはならない」
「その2 休職命令により、従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、この者が年次有給休暇を申し出たときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇を申し出ることはできない」 |
継続勤務とは(S63.3.14基発150)
「継続勤務とは労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては勤務の実態に即し
実質的に判断すべきものであり、
次に掲げるような場合を含むこと。
この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
①定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当を支給した場合を含む)。
ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合は除く。
②臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、6か月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
③臨時工、パート等を正規社員に切替えた場合
④在籍型の出向をした場合
⑤休職とされていた者が復職した場合
⑥会社が解散し、従業員の待遇等を含め、権利義務関係が新会社に包括承継された場合
⑦全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合等。 |
半日休暇
「39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」(S63.3.14基発150)
⇒ 半日の有給休暇を請求されても応じる義務はない。ただし、
労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合、かつ本来の1日単位の取得の阻害とならない範囲内で運用される限り、構わないとされてきた。
さらにH22.04.01以降は、39条4項に基づいて、労使協定の締結により、時間単位での有給休暇も認められるようになった。 |
繰越と時効
「就業規則で」年次有給休暇は翌年度に繰り越してはならない」と定めた場合、できるだけ年度内に年次有給休暇をとらせる趣旨の規定を設けることは差支えないが、かかる事項を就業規則に規定しても、年度経過後のおける年次有給休暇の権利は消滅しない」(S23.5.15基発686)
⇒ 消滅時効は「有給休暇の取得権利が発生した日から2年である」 |