10
D |
�����N���@ ��b�m���Ɗ֘A�ߋ����@Tome�mHome�� |
| �@�Ǖw�N�� |
�֘A�ߋ���@11-1A�A11-1B�A11-1C�A11-1D�A11-1E�A12-1B�A13-4B�A13-10E�A14-3C�A14-6A�A14-6E�A15-2E�A16-10D�A17-3A�A17-3E�A17-8C�A18-3B�A19-6E�A20-2D�A20-3A�A20-4D�A21-8E�A22-10E�A23-3B�A24-4�A�A24-4�C�A24-4�E�A24-4�G�A26-2D�A27-2�I�A28-2D�A29-8D�A30-6B�A�ߌ��4�d�A��2-4E�A��2-9A�A��4-3B�A��5-1E�A��5-2D�A��6-3B
�@29-2�I���A��4-2�I�� |
| �֘A�@�Ǖw�N���̎x���v��(49��)�A�N���z(50��)�A����(51��)�A�x����~(52��) |
| �ʃy�[�W�f�ځF���S�ꎞ���A�⑰��b�N���A�V���b�N���̌J�グ |
�@��
�w
�N
��
��
�x
��
�v
�� |
1�D�Ǖw�N���̎x���v��(49��)�@�@����(R03.04.01)�A�@����(H29.08.01)
�@��Ǖw�N���́A���S���̑O���ɂ��������S���̑����錎�̑O���܂ł̑�1����ی����Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW��ی����[�t�ϊ��Ԃƕی����Ə����ԂƂ����Z�������Ԃ�10�N�ȏ��ł���v(�ی����[�t�ϊ��Ԗ��͊w���[�t����ȊO�̕ی����Ə����Ԃ�L����҂Ɍ���)�����S�����ꍇ�ɂ����āA�v�̎��S�̓����v�ɂ�������v���ێ����A���A�v�Ƃ̍����W(�͏o�����Ă��Ȃ����A�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ���ꍇ���܂�)��10�N�ȏ�p������65�Ζ����̍�������Ƃ��ɁA���̎҂Ɏx������B
�@�������A�V���b�N���܂��͏�Q��b�N���̎x���������Ƃ�����v�����S�����Ƃ��́A���̌���łȂ��
�@�2���@37����2��3��(�⑰��b�N���ɌW�鐶�v�ێ��v��)�̋K��́A�O���̏ꍇ�ɏ��p����B���̏ꍇ�ɂ����āA����3�������ی��Җ��͔�ی��҂ł����ң�Ƃ���̂́A��v��Ɠǂݑւ�����̂Ƃ��飁@
�ˉǕw�N���ɌW�鐶�v�ێ��v���́A�{�s��6����4�Œ�߂�B
�@��̓I�ɂ���������B
�@�3���@60�Ζ����̍ȂɎx������Ǖw�N���́A�Ȃ�60�ɒB�������̑����錎�̗�������A���̎x�����n�߂飁@

(1)�Ǖw�N���ɌW�鐶�v�ێ��v��
�@���v�ێ��F������v�����S������
�A���̎��_�ɂ��������v�������A���������ɂ킽��������(���邢�͏���)�����l�����ł��邱�ƁA
�B����(���邢�͏���)�̗v���́A��̓I�ɂ́A�ʒB(H23.03,23�N��03213)�ɂ��B
�@���S�̓����A�O�N(���m��̏ꍇ�͑O�N)�̎����̎��т��N�z850���������邢�͏����̎��т��N�z655.5���~�����A���邢�́A���S�̓����A�����ނ�5�N�ȓ��ɁA������850���~���邢�͏�����655.5���~�z�����ɂȂ�������܂�邱���B
�C���v����̗v���́A�ʒB(H23.03.23�N����������2)�ɂ��B
(2)���̑��̕⑫
�E��Ǖw��Ƃ͢�v�Ɏ��ʂ������A���S�l�(�L����)
�@��ی����[�t�ϊ��Ԃƕی����Ə�����(�w���[�t������ԁA�[�t�P�\���Ԃ��܂�)�����Z����10�N�ȏ㣂ł���A���A�ی����[�t�ϊ��Ԗ��͊w���[�t����E�[�t�P�\���ԈȊO�̕ی����Ə����Ԃ�1�J���ȏ������(�N���z��0�~�Ƃ͂Ȃ�Ȃ���)�Ɍ�����B
�A�x�����ԁF�Œ��ŁA60�Γ��B���̗�������65�Γ��B���܂ł�5�N�ԁA
�@�v�̎��S���ɍȂ�60�Έȏ�̏ꍇ�́A�Y������(�v�����S����)���̑����錎�̗�������x�������B
�B�����Ȃ��A�⑰�����N���̎�������Ƃ��́A60����65�܂ł͉Ǖw�N���ƈ⑰�����N���̂����ꂩ�̑I���ƂȂ�B
 �`���b�ƕ⑫ �`���b�ƕ⑫
�@��Q��b�N���̎x���������Ƃ�����Ƃ��x�����Ȃ��B
�@��������N���@�ɂ���Q�N��(��Q�����N��������)�͏�Q��b�N���Ƃ݂Ȃ��(���a60�N�����@����29��2��)
�ˢ�����̗̎L���ɂ�����炸�ْ�����ꍇ�͎x�����Ȃ��(S35����48)�Ƃ��������A�ߘa3�N�̖@�����ɂ��A�j�����ꂽ�B
�@�����擾�������A�擾���Ɏ��S�����ꍇ�́A������Ƃ��Ȃ���ɊY������B�Ȃ��A���擾���̗����ȍ~�Ɏ��S�����ꍇ�́A�܂���������Ă��Ȃ��ꍇ�ł����Ă��A������Ƃ����飂ɊY�����A���x���N������������B�@
�A�V���b�N���̎x���������Ƃ�����Ƃ��͎x�����Ȃ��B
�@����ł́A65�ɂȂ��Ă��V���b�N���̎�������̂ɍْ萿�������Ȃ��܂܂̏�ԂŁA���S�����Ƃ��͂ǂ����B
�@����ɂ��ẮA�ŋ߂������J���Ȃ̉���(H29.03.24)�ɂ��A
�E��V���b�N���̎x�����Ă����Ƃ���Ƃ́A�V���b�N���̐������s���x�������Ă����҂����ɂƂǂ܂炸�A���Ɋ�Â��x�������ƂɎx�������̂Ƃ���鋋�t�̢�x�����錠��(�x����)����������������Ɖ����邱�Ƃ��Ó��ł���B
�E�������A�V���b�N���̎x���̌J�艺�����s���܂ŁA�x������������ӎv�̂Ȃ��������̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���ꍇ�ɂ́A��V���b�N���̎x�����Ă����Ƃ���ɓ�����Ȃ��Ɖ��߂���B
(�������A�V��ސE���t�����������̔N�����t�̎���L���Ă��炸�A�V���b�N���̎���������5�N���o�߂�����̑����錎�̖����܂łɎ��S�����ꍇ�Ɍ���)
�@�܂��A���̏ꍇ�́A�x������������ӎv�̖����������Ƃ��ؖ����鏑�ނ̓Y�t���K�v�ł���B
�˒P�Ȃ鐿�����u�̏ꍇ�́A�V���b�N���̎x�������������Ă���Ƃ݂Ȃ���A�Ǖw�N���̎��͔������Ȃ��̂ŁA�Ȃ͖��x���̋��t�𐿋����邱�ƂɂȂ�(���̏ꍇ�A����5�N���K�p�����)
�ˌJ�艺���Ҋ��̂��߂ɐ������Ȃ������Ƃ����ӎv���ؖ�������̂�����A�x�����͔������Ă��Ȃ��Ƃ���A�Ǖw�N�������x���̘V���b�N���̂����ꂩ��I���ł���B
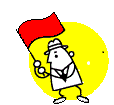
�V���b�N���̎��������������Ɏ��S�����ꍇ�́A�x�����̔����̗]�n�͂Ȃ�(�x���͎������̗�������ł��邽��)�̂ŁA��V���b�N���������Ƃ��Ȃ���ɊY������B
�@�Ǖw�N���̎�|
�@�V���b�N���̎��i����(������25�N�ȏ�A���݂�10�N�ȏ�)�������v�����S�����ꍇ�ł����Ă��A�v�������N���ɉ����������Ƃ��Ȃ���A���̍ȂɈ⑰�����N���͎x������Ȃ��B
�@���A�ȂɎq�����Ȃ������邢�͂��Ă�����18�Γ��B�N�x���������Ă���A�⑰��b�N���̎x�����Ȃ��B
�@���̂��߂ɁA���̓�̎�|����Ǖw�N�����������ꂽ�B
�@60����65�܂ł̍Ȃ̐����̈���
�˕v�̎��S�ڂ̎x�����R�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A60����65��(��b�N���̎J�n)�܂łɎx���������ʎx���̘V������N���̂悤�Ȑ��i
�A�v���i�N�������ی����̊|���̂Ėh�~
|
11
1C |
�@�Ǖw�N���́A���S���ɂ����Ď��S���̑����錎�̑O���܂ł̑�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW��ی����[�t�ϊ��Ԃƕی����Ə����Ԃ����Z�������Ԃ�10�N�ȏ゠��v�����S�����ꍇ�ɁA���̎��S�����҂̍ȂɎx������B(H30�N�x��)(��b) |
|
��������� |
|
��
��
4E |
�@���S���̑O���ɂ����Ď��S���̑����錎�̑O���܂ł̑�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW��ی����[�t�ϊ��Ԃ�5�N�ƍ��Z�Ώۊ��Ԃ�5�N�L����v�����S�����ꍇ�A����̗v�������ȂɉǕw�N�����x�������B�Ȃ��A���Y�v�͏�L���ԈȊO�ɑ�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��Ԃ�L���Ȃ����̂Ƃ���B(11-1C�̗ތ^) |
|
��������� |
|
��
5
2D |
�@�����N����2����ی��҂Ƃ��Ă̕ی����[�t�ϊ��Ԃ�15�N�ł���A���̔�ی��҂Ƃ��Ă̕ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃ�L���Ȃ��v�����S�����ꍇ�A���Y�v�̎��S�������v���ێ����A�����W��15�N�ȏ�p������60�̍Ȃ��������ꍇ�ł��A�Ǖw�N���͎x������Ȃ��B�Ȃ��A���S�����v�́A�V���b�N�����͏�Q��b�N���̎x���������Ƃ��Ȃ����̂Ƃ���B(11-1C�̗ތ^) |
|
��������� |
|
| �������̂��߂̔N�ߗv�� |
15
2E |
�@�v�̎��S�����A�v�Ƃ̍����W��10�N�ȏ�p�����Ă���A�v�ɂ���Đ��v���ێ�����Ă����Ȃ��A65�Ζ����ł���Ƃ��Ǖw�N���̎��͔������Ȃ��B(��b) |
|
��������� |
|
20
3A |
�@�Ǖw�N���́A�v�̎��S�����v�ɂ���Đ��v���ێ����A���A�v�Ƃ̍����W(�͏o�����Ă��Ȃ���������̍����W�Ɠ��l�̎���ɂ���ꍇ���܂�)��10�N�ȏ�p������60�Έȏ�65�Ζ����̍ȂɌ��������������B(15-2E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
��
4
3B |
�@��1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW��ی����[�t�ϊ��Ԃ�25�N�ȏ゠��A�V���b�N���y�я�Q��b�N���̎x���������Ƃ��Ȃ��v�����S�����ꍇ�ɂ����āA���S�̓������Y�v�ɂ���Đ��v���ێ����A���A�v�Ƃ̍����W��10�N�ȏ�p�������Ȃ�60�Ζ����ł���Ƃ��́A�Ǖw�N���̎�����������B(15-2E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
| ����C�Ӊ�����ی��� |
17
8C |
�@����ɂ��65�Έȏ�̔C�Ӊ�����ی��҂����S�����ꍇ�A���S�ꎞ���͎x������邪�Ǖw�N���͎x������Ȃ��B(���p) |
|
��������� |
|
��
2
9A |
�@68�̕v(���a27�N4��2�����܂�)�́A65�Έȏ�̓���ɂ��C�Ӊ�����ی��҂Ƃ��ĕی�����[�t���A�ߘa2�N4���ɘV���b�N���̎��i���������A�ْ萿���̎葱��������O�Ɏ��S�����B
�@���S�̓����A���Y�v�ɂ�萶�v���ێ����A���Y�v�Ƃ̍����W��10�N�ȏ�p������62�̍Ȃ�����ꍇ�A���̍Ȃ��J�グ�x���̘V���b�N�������Ă��Ȃ���A�Ȃɂ�65�܂ʼnǕw�N�����x�������B
�@�Ȃ��A���S�������Y�v�́A��Q��b�N���̎x���������Ƃ��Ȃ��A�w���[�t����̊��ԁA�[�t�P�\�̊��ԁA��2����ی��Ҋ��ԋy�ё�3����ی��Ҋ��Ԃ�L���Ă��Ȃ����̂Ƃ���B(17-8C�̗ތ^)(R03��) |
|
��������� |
|
��
��
�� |
26
2D
|
�@�Ǖw�N���̎x���ΏۂƂȂ�Ȃ́A�v�Ƃ̍����W��10�N�ȏ�p�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̍����W�ɂ́A�����̓͏o�����Ă��Ȃ��������㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ������ꍇ���܂܂Ȃ��B |
|
��������� |
|
11
1E |
�@�Ǖw�N���́A�v�����S�����ꍇ�ɂ����āA�v�̎��S�����v�ɂ���Đ��v���ێ����A���A�v�Ƃ̍����W��(�͏o�����Ă��Ȃ����A�����㍥���W�Ɠ��l�̎���ɂ���ꍇ���܂�)��5�N�ȏ�p������65�Ζ����̍ȂɎx������B(26-2D�̗ތ^) |
|
��������� |
|
�v
��
�V
��
��
�b
�N
��
�E
��
�Q
��
�b
�N
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
�� |
11
1D |
�@�Ǖw�N���́A���S�����v����Q��b�N���������Ƃ�����Ƃ��͎x������Ȃ��B(��b)(R03��) |
|
��������� |
|
20
4D |
�@�Ǖw�N���́A���S�����v����Q��b�N���������Ƃ�����Ƃ��ɂ͎x������Ȃ��B(11-1D�̗ތ^)(R03��) |
|
��������� |
|
18
3B |
�@���S�����v����Q��b�N���̎��҂ł��������Ƃ������Ă��A���ۂɎx���������Ƃ��Ȃ���ΉǕw�N���͎x�������B(11-1D�̉��p) |
|
��������� |
|
29
2
�I
�� |
�@�����N���@��49���ł́A�Ǖw�N���́A���̕ی����̔[�t�̗v���������v�����S�����ꍇ�ɂ����āA�v�̎��S�̓����v�ɂ���Đ��v���ێ����A���A�v�Ƃ̍����W��10�N�ȏ�p���������̍Ȃ�����Ƃ��Ɏx������邪�A|�@C�@|�͎x������Ȃ����Ƃ��K�肳��Ă���B
�@�v�����S��������53�ł������ȂɎx������Ǖw�N���́A|�@D�@|����A���̎x�����n�߂�B(R03��) |
|
�E��������� |
��Q�͂������ |
17
3A |
�@���S�����v���������N���@�ɂ���Q�����N�������������Ƃ�����ꍇ�A�Ǖw�N���͎x������Ȃ��B(11-1D�̔��W)(R03��) |
|
��������� |
|
14
6A |
�@�Ǖw�N���́A���S�����v���V���b�N���̎x���������Ƃ�����Ƃ��ɂ͎x������Ȃ��B(��b) |
|
��������� |
|
��
2
4E |
�@�v���V���b�N���̎����擾�������Ɏ��S�����ꍇ�ɂ́A���̗v�������Ă��Ă��A���̎҂̍ȂɉǕw�N���͎x������Ȃ��B(���W) |
|
��������� |
|
| �Ȃ��⑰�N���̎��� |
22
10
E |
�@�v�̎��S�ɂ��⑰��b�N���̎���L�������Ƃ̂���Ȃɂ́A�Ǖw�N���͎x������Ȃ��B(�d�v) |
|
��������� |
|
29
8D |
�@���v����������1����ی��҂̕v�����S���A�Ȃ��⑰��b�N���̎��҂ƂȂ����ꍇ�ɂ́A�ȂɉǕw�N�����x������邱�Ƃ͂Ȃ��B (22-10E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
27
2� |
�@60�Ζ����̍Ȃ�����L����Ǖw�N���́A�Ȃ�60�ɒB�������̑����錎�̗�������x������邪�A���̂Ƃ��ɍȂ���Q��b�N���̎���L���Ă���ꍇ�ɂ́A�Ǖw�N���̎��͏��ł���B(���p) |
|
��������� |
|
�x
��
��
�� |
11
1A |
�@60�Ζ����̍ȂɎx������Ǖw�N���́A�Ȃ�60�ɒB�������̑����錎����A���̎x�����~����B |
|
��������� |
|
17
3E |
�@�v�̎��S�����A�v�ɂ���Đ��v���ێ����ꂽ�v�Ƃ̍����W���p������10�N�ȏ゠��Ȃɂ��ẮA�v�̎��S�����A�N�60�Ζ����ł����Ă��Ǖw�N���̎��͔������邪�A�x���J�n��60�ɒB�������̑����錎�̗�������ł���B(��b) |
|
��������� |
|
20
2D |
�@�v�̎��S�̓�����60�Ζ����ł������ȂɎx�������Ǖw�N���́A�Ȃ�60�ɒB�������̑����錎�̗�������x�����J�n����A65�ɒB�������̑����錎�܂Ŏx�������B(17-3E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
12
1B |
�@�v�̎��S����60�Ζ����̍ȂɎx������Ǖw�N���́A�Ȃ�60�ɒB�������̑����錎����x�����J�n����B(17-3E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
��
�w
�N
��
��
�z |
2�D�N���z(50��)�@
�@��Ǖw�N���̊z�́A���S���̑����錎�̑O���܂ł̑�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW�鎀�S���̑O���ɂ�����ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃɂ��A27���̋K��(�V���b�N���̔N���z�̌v�Z)�̗�ɂ���Čv�Z�����z��4����3�ɑ�������z�Ƃ��� |
11
1B |
�@�Ǖw�N���̊z�́A�v�̎��S���̑����錎�܂ł̑�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW�鎀�S���̑O���ɂ�����ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃɂ��āA�V���b�N���̊z�̌v�Z�̗�ɂ��v�Z�����z��3����2�ɑ�������z�Ƃ���Ă���B(��b) |
|
��������� |
|
14
6E |
�@�Ǖw�N���̊z�́A�v����1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��Ԃɂ��Ď��ׂ��ł������V���b�N���̊z��4����3�ł���B(11-1B�̗ތ^) |
|
��������� |
|
19
6E |
�@�Ǖw�N���̊z�́A���S���̑����錎�̑O���܂ł̑�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW�鎀�S���̑O���ɂ�����ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃɂ��A�V���b�N���̌v�Z���@�ŎZ�o�����z��4����3�ɑ�������z�ł���B(11-1B�̗ތ^) |
|
��������� |
|
28
2D |
�@�Ǖw�N���̊z�́A���S���̑����錎�̑O���܂ł̑�1����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW�鎀�S���̑O���ɂ�����ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃɂ��A�����N���@��27���̘V���b�N���̊z�̋K��̗�ɂ���Čv�Z�����z�Ƃ���Ă���B
(11-1B�̗ތ^) |
|
��������� |
|
��
4
2
�I
�� |
�@�Ǖw�N���̊z�́A���S���̑����錎�̑O���܂ł̑�P����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��ԂɌW�鎀�S���̑O���ɂ�����ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃɂ��A�����N���@��27���̘V���b�N���̊z�̋K��̗�ɂ���Čv�Z�����z��|�@B�@|�ɑ�������z�Ƃ���B |
|
�Ɖ�������� |
��Q�͂������ |
23
3B |
�@�Ǖw�N���̊z�́A���S���̑����錎�̑O���܂ł̕v�̑�1����ی��҂ɌW��ی����[�t�ϊ��ԋy�ѕی����Ə����Ԃ����ƂɎZ�肳��邪�A�����ی�@�ɂ�鐶���}�����Ă������ߕی����[�t��Ə�����Ă����������̌v�Z�̊�b�Ɋ܂܂��B(11-1B�̗ތ^) |
|
��������� |
|
16
10
D |
�@��1����ی��҂Ƃ��ĕی����[�t�ϊ���20�N�A�ی����S�z�Ə�����5�N�A�ی������z�Ə����Ԃ�5�N(�����������21�N3���܂ł̊��ԂɌ���)�ł������v�����S�����ꍇ�̉Ǖw�N���̔N���z���Z�肷���ŁA�ی������z�Ə����Ԃ͕ی����[�t�ϊ��Ԃ�3����2�Ƃ��ĕ]�������B(H21��)(���p) |
|
��������� |
|
24
4� |
�@�Ǖw�N���̊z�̎Z��ɂ́A���S�����v����2����ی��҂Ƃ��Ă̔�ی��Ҋ��Ԃ�L���Ă����Ƃ��Ă��A���Y���Ԃ͔��f����Ȃ��B(��b) |
|
��������� |
|
��
�w
�N
��
�z
��
�t
��
�N
�� |
13
10
E |
�@�Ǖw�N���̔N���z�ɂ́A�t���ی����̔[�t�̗L���͉e�����Ȃ��B(��b) |
|
��������� |
|
21
8E |
�@�Ǖw�N���̊z�́A���S�����v�̘V���b�N���z�̌v�Z�̗�ɂ���Čv�Z�����z��4����3�ɑ�������z�ł��邪�A���Y�v���t���ی����[�t�ϊ��Ԃ�3�N�ȏ�L���Ă����ꍇ�ɂ́A���Y�z��8,500�~�����Z�����z�ł���B(13-10E�̉��p) |
|
��������� |
|
��
5
1E |
�@�Ǖw�N���̊z�́A���S�����v�̘V���b�N���̌v�Z�̗�ɂ���Čv�Z�����z��4����3�ɑ�������z�ł��邪�A���Y�v��3�N�ȏ�̕t���ی����[�t�ϊ��Ԃ�L���Ă����ꍇ�ɂ́A��L�̊z��8,500�~�����Z�����z�ƂȂ�B(21-8E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
24
4� |
�@�t���ی����̔[�t�҂����S�����ꍇ�ɂ�����Ȃɑ���Ǖw�N���̊z�́A�v�����͂��ł������V���b�N���̕t���N��������2����1�����z�����Z�����B(21-8E�̗ތ^) |
|
��������� |
|
��
��
�E
�x
��
��
�~
�� |
3.1�@����(51��)
�@��Ǖw�N���̎��́A���҂�65�ɒB�����Ƃ��A����40��1���e��(�⑰��b�N���̎������R)�̂����ꂩ�ɊY������Ɏ������Ƃ��́A���ł����
| 1 |
�@���S�����Ƃ� |
| 2 |
�@�����������Ƃ� |
| 3 |
�@�{�q�ƂȂ����Ƃ�(���n�������͒��n�����̗{�q�ƂȂ����Ƃ�������) |
3.2�@�����F�V���b�N���̌J��ɔ�������(����9����2��5���A��9����2��2��6��)
�@��Ǖw�N���̎��́A�S���J�グ�A�ꕔ�J�グ�ɂ��V���b�N���̎����擾�����Ƃ��́A���ł����
�ˁ@�J�グ�ɔ����Ǖw�N���̎����ɂ��Ă͂������
3.3�@�x����~(52��)
�@��Ǖw�N���́A���Y�v�̎��S�ɂ���41��1���ɋK�肷�鋋�t(�J����@�̋K��ɂ��⑰�⏞)���s����ׂ����̂ł���Ƃ��́A���S������6�N���A���̎x�����~���飁@
���J��@79���ɂ��⑰�⏞�͕��ϒ�����1,000����(�������̏ꍇ�́A180����/�N��6�N��)
�ˢ���S�̓�����6�N�Ԏx����~��ł���B(�⑰��b�N���A�⑰�����N��������)
�@�������A�Ǖw�N���̎��Ԃ�60����65�܂łł��邩��A�v�̎��S���ɂ�����Ȃ̔N��ɂ���āA���ۂ̎x����~�������قȂ�B
�@�Ⴆ�A�v�̎��S���ɍȂ�54�Ζ����ł���A�x����~�Ȃ��A60����5�N�ԉǕw�N�����ł��邪�A�v�̎��S���ɍȂ�57�ł��ꂪ�A6�N�̎x����~���Ԃ��I������63����2�N�Ԃ̎ƂȂ�B
3.4�@�x�������@
�E���S�ꎞ���ƉǕw�N���͂ǂ��炩��I���B���S�ꎞ���Ƃ̎x�������ɂ��Ă͂��������B
�E�⑰��b�N���͎��S�ꎞ�������D��B
�E�⑰��b�N���ƉǕw�N���͂����ꂩ��I���B
�ˉǕw�N���ƈ⑰��b�N���̎��͗����Ƃ���������̂ŁA���Ƃ��Έ⑰��b�N���̎��I��������A�Ǖw�N���̎����܂��c���Ă���A���̌�A�Ǖw�N�������邱�Ƃ͂ł���
�E���S�ꎞ���A�⑰��b�N���A�Ǖw�N���O�Ƃ��ł������ȂƂ��́A�����ꂩ������I���ł��Ȃ��B�@
�E�⑰�����N���̎�������Ƃ��́A60����65�܂ł͉Ǖw�N���ƈ⑰�����N���̂����ꂩ�̑I���ƂȂ�B�����A�⑰�����N����I�������ꍇ�́A���S�ꎞ�����ł���B |
��
��
��
��
�~
�� |
24
4� |
�@�Ǖw�N���̎��҂ł���Ǖw��65�ɒB�����Ƃ��ɘV���b�N���̎��i�����Ă��Ȃ������ꍇ�ł��A�Ǖw�N���̎��͏��ł���B(��b) |
|
��������� |
|
13
4B |
�@�Ǖw�N���́A���҂������������Ƃ��́A���̎x�����~����B(��b) |
|
��������� |
|
24
4� |
�@�Ǖw�N���̎��́A���҂����n�������͒��n�����̗{�q�ƂȂ����Ƃ��Ă��A����𗝗R�ɁA���ł��邱�Ƃ͂Ȃ��B(��b) |
|
��������� |
|
14
3C |
�@�Ǖw�N���̎��́A�v�̎��S�ɂ��⑰�����N�����ł���Ƃ��ɂ́A���ł���B |
|
��������� |
|
| �J��@�Ƃ̒��� |
30
6B |
�@�Ǖw�N���́A�v�̎��S�ɂ��ĘJ����@�̋K��ɂ��⑰�⏞���s����ׂ����̂ł���Ƃ��́A���S������6�N�ԁA���̎x������~�����B |
|
��������� |
|
��
�U
3B |
�@�J����@�̋K��ɂ���Q�⏞���邱�Ƃ��ł���Ƃ��ɂ������Q��b�N�����тɓ��@�̋K��ɂ��⑰�⏞���s����ׂ����̂ł���Ƃ��ɂ�����⑰��b�N�����͉Ǖw�N���ɂ��ẮA6�N�ԁA���̎x�����~����B(30-6B�̗ތ^) |
|
��������� |
|